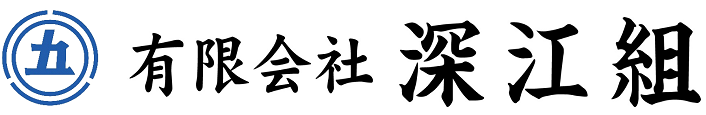二十四節気(にじゅうしせっき)というのをご存知でしょうか?
例えば、春分・夏至・秋分・冬至などがそうであり、私達が日常的に使っている言葉の中にも数多く登場します。
私達は、その言葉を聞いただけで季節感を感じ取り、思い出さえも蘇ることがあります。
この記事では、二十四節気について簡単にご紹介したいと思います。
ぜひ、季節の節目を感じ取って下さい。
目次
二十四節気とは
そもそも二十四節気とは何でしょう?
これは、古代中国で考案されたもので、太陽の動きをもとにして作られており、一年を24等分したものです。
一年を春夏秋冬の季節で分けると四等分ですね。
各季節ごとに6つの節気があり、24節気となります。
冬至があり、小寒、大寒、立春、雨水、啓蟄、春分となります。
一つの節気は15日間あります。
毎年同じ日とは限りません。
二十四節気は、太陽の動きから作られているので季節を感じやすく、農作業などでは重宝されていたようです。
ただし、もともとが中国で作られたものであることから、日本と中国の地理的な気候の違いに起因して、季節感が合わない言葉があります。
よく「暦の上では春です」などと聞きますが、感覚がズレるのはこれが原因でしょうね。
花庭ライン公式アカウントでは、二十四節気に関する情報を約15日ごとに発信中!

春の節気
【2月】に属する節気
立春(りっしゅん)

2月4日頃
まだ寒さは厳しいが、陽射しは春めいてくる頃。
旧暦の正月にあたります。そのため、2月3日の節分は大晦日にあたります。
立春を過ぎてから初めて吹く強い南風を「春一番」といいます。
【立春大吉】
禅寺では、門口にこの御札を貼り招運来福を願うとのこと。
また、文字が左右対称になっており、縁起が良いとも言われています。
梅の花と桜の花はよく似ているので、間違える方も多いようです。
梅の花は丸く、桜に花はギザギザなんです。
ちなみに、現代では「花見といえば桜」ですが、奈良時代には「花見といえば梅」だったそうです。
雨水(うすい)

2月19日頃
それまで降っていた雪が雨に変わる頃。
実際にはまだ雪深い地域もあるが、凍っていた大地がゆるんで草木が芽生える時期。
雪解け水で土が潤い、農耕の準備を始める目安とされました。
雛人形を雨水に飾ると、良縁に恵まれるという言い伝えもあります。
【ひな人形】
立春(2月4日頃)を迎えたら飾ってよいと言われますが、次に良いのが雨水。
ひな人形は水に関係する行事のため、「水が豊かになる雨水にひな人形を飾り始めると良縁に恵まれる」と言われている。
【春一番】
立春(2月4日ごろ)から春分(3月21日ごろ)までの間に初めて吹く強い南風のこと。
春一番は毎年必ず吹くわけではなく、観測なしの年もある。
気象庁による認定なしだが、「春二番」や「春三番」というのもある。
しかし、そのときは「春疾風(はるはやて)」「春嵐」等と呼び名が変わる
【3月】に属する節気
啓蟄(けいちつ)

3月5日頃
厳しい冬を超えるために地中で冬眠していた虫たちが姿を表す頃
「啓」は“開く・開放する”、「蟄」は“虫が冬の間、土にこもる”といった意味があり、「啓蟄」は春の到来を感じて生き物たちが土から出てくることを表しています。
【菰はずし】
冬の間、松を害虫から守るためには藁でできた菰(こも)を巻きますが、菰を取り除く「菰はずし」は、「啓蟄」に合わせて行う地域が多く季節の風物詩となっています。
【東大寺のお水取り】
歴史と伝統のまち奈良で、1200年以上にわたって続く伝統行事。
東大寺二月堂で行われる「修二会(しゅにえ)」という法会の一行事 です。
3月1日から3月14日の毎晩行われ、お松明の火の粉を浴びると、1年間無病息災に過ごせて幸せになるといわれる。
春分(しゅんぶん)

3月21日頃
昼と夜の時間が等しくなります。
春分の前後3日を含めた7日間を「お彼岸」と言います。
国立天文台で和歌山の日の出と日の入りを調べてみました。
日の出 06:03
日の入り 18:11
和歌山の事実 昼間が12時間8分 夜間が11時間52分
何と! 昼間の方が長かったんです。
何十年と信じてきたことが覆った瞬間でした。
【お彼岸】
春分の日を中日(ちゅうにち)として、前の3日間と後ろの3日間、計7日間を「彼岸」という。
「春のお彼岸」ともいう。
今年の場合は、3月17日が「彼岸入り」、3月23日が「彼岸明け」となります。
この期間に行う仏事を「彼岸会(ひがんえ)」という。
秋分の日にも同じく「秋のお彼岸」と呼ばれる彼岸がある
【4月】に属する節気
清明(せいめい)

4月5日頃
清明は、清浄明潔(しょうじょうめいけつ)という言葉の略。
意味は、「万物が成長し、清らかに、かつ、鮮やかに見える」です。
春の季語にもなっています。
西日本では花見の時期です。
【初ガツオ】
この時期に獲れるカツオが「初鰹」または「上り鰹」と呼ばれます。
また、8月下旬~9月に獲れるカツオは「戻りガツオ」です。
【清明祭】
沖縄では「シーミー(清明節)」と呼び、お盆のように親族一同がお墓参りしたり先祖供養を行います。
【玄鳥至(つばめきたる)】
ツバメが渡来する時期
【 鴻雁北 (こうがんかえる)】
日本で越冬した冬鳥の雁が北へ帰るころ
穀雨(こくう)

4月20日頃
この時期に降雨を「百穀春雨ひゃっこくはるさめ」といって、この頃に種を蒔くと、雨に恵まれよく成長すると言われています。
後半には、八十八夜があり新茶の美味しい季節となります。
【八十八夜】
立春から数えて88日目の意味を持つ八十八夜の有名な行事としては、童謡の「茶摘」でもおなじみの新茶を摘む茶摘みがあります。
【朧月(おぼろづき)】
春の夜などの、ほのかにかすんだ月。
春の季語。
朧月を調べる中で見つけた俳句を紹介します。
加賀千代女 作 『 何事か ある身にはよき 朧月 』
隠し事がある身には、はっきり見える月明かりよりも朧月のぼんやりさが都合がいいと詠んでいる一句。
夜の出来事として、色恋沙汰を想像してしまいそうですが……。
 新緑
新緑
夏の節気
【5月】に属する節気
立夏(りっか)

5月5日頃
暦の上ではこの日から夏の始まりです。
気温も上がり夏の兆しが見え始める頃です。
【鯉のぼり】
5月5日はこどもの日(端午の節句)
鯉のぼりには、艱難も多く生々流転とする人生をも「鯉の滝登り」のように、負けずに向上していく、立身出世への親の願いが込められています。
中国の「登竜門」などの伝説に由来
【しょうぶ湯】
菖蒲は、古来より病気や病を払う薬草といわれる。
端午の節句に、菖蒲湯に入ることで厄除けや健康祈願の風習となった。
【母の日】
第二日曜日、今年は12日ですね。
カーネーションを送るのは、116年前のアメリカでの出来事による。
一人の女性が、母親の命日に母親が好きだった白いカーネーションを教会で配ったのが始まり(諸説あり)
小満(しょうまん)

5月21日頃
夏の作物が身を膨らませ出す頃です。
「気候が良くなり、万物が次第に成長し満ち始める」の意味。
また、秋にまいた麦が冬を経て春に成長する様子に、少し満足する(小満足)から「小満」とする説もあり。
作物の成長が命をつなぐことになるので、安心感が込められています。
【紅花栄(べにばなさかう)】
現在も口紅の「紅」の原料となる紅花が開花する時期。
染料としても用いられ、咲き始めに外側からこまめに摘んで使用「末摘花(すえつむはな)」 油の原料にも。
【麦秋(ばくしゅう/むぎあき)】
冬に種を蒔いた麦が成熟し収穫期を迎える。
初夏なのに秋というのは、米を収穫する「収穫の秋」をなぞらえている。
麦の穂が黄金色になる様子は、稲穂が黄金色になる様子に通じる情景ですね。
初夏の季語
【6月】に属する節気
芒種(ぼうしゅ)

6月6日頃
稲や麦の種を蒔く頃のようですが、実際にはもっと早く蒔くので農家が忙しくなる時期です。
米や麦など穂の出る穀物を蒔く時期という意味。
この時期には、暑さ・湿度も日に日に増し、西日本でも梅雨入りが発表される頃。
「芒」の漢字の意味は、稲穂や麦穂の穂先の尖った毛を指します。
【日本三大御田植祭】
その年の五穀豊穣を祈る祭り。
重労働である田植えを楽しみながらできるように、笛・太鼓や唄で踊ったりしながら行う様子が文献や屏風に描かれている。
香取神宮 御田植祭:千葉県香取市
伊雑宮(いざわのみや) 磯部の御神田:三重県志摩市
住吉大社 御田植神事:大阪府大阪市
【紫陽花】
日本原産(sun)の落葉低木。
梅雨(rainy)を象徴する花。
酸性の土では青色・アルカリの土では赤色に花色を変える。
夏至(げし)

6月21日頃
太陽の位置が一番高くなり、昼間の時間が一番長くなり、夜の時間が一番短くなる。
冬至に比べて、4時間ほども昼の時間が長くなるそうです。
「夏に至る」と書くように、この頃から夏の盛りに向かいます。
また、良く知られたこととして「1年で最も日中が長い日」であります。
しかし、日の出が一番早い日でも、日の入りが一番遅い日でもありません!
ご存知でしたか⁉️
和歌山県で調べると
早い日の出は、6/6~6/19までの4:47
遅い日の入りは、6/21~7/6までの19:15
実は、札幌の方が日照時間が長いようです。
日本平均では、14時間50分程度
【二見興玉神社(ふたみおきたま)】
三重県伊勢市二見町江にある神社で、夏至祭が有名。
二見浦にある夫婦岩の間から差し昇る「日の大神」を拝する。
【7月】に属する節気
小暑(しょうしょ)

7月7日頃
小暑から大暑を「暑中」と呼び、暑中見舞いを出す頃。
だんだん暑さが増していく頃という意味。
梅雨明けも近く急な集中豪雨がある。
また、ジメジメした日も続き、その中にも夏の熱気が感じる時期。
【熱中症】
私の子供のころは日射病と呼ばれていました。
熱中症とは、直射日光だけを原因とせず、高温多湿の環境によって引き起こす体調不良の総称。
対策として、エアコンの利用やスポーツドリンクの活用、十分な睡眠等。
主体的に天気予報を参考にして、高温多湿を避けること。
無理をせず、異変を感じたら受診を!
大暑(たいしょ)

7月23日頃
暑さが最も厳しくなる頃です。
日に日に暑さが増し、ジメジメじとじとする蒸し風呂のような日もあります。
今年の暑さは昨年に匹敵との予報、熱中症対策が必須。
【熱中症】
熱中症とは、直射日光だけを原因とせず、高温多湿の環境によって引き起こす体調不良の総称。
対策として、エアコンの利用やスポーツドリンクの活用、十分な睡眠等。 主体的に天気予報を参考にして、日中の外出を控え高温多湿を避けること。
無理をせず、異変を感じたら受診を!
【打ち水】
昔から伝わる夏の風物詩エコな暑さ対策ですが、効果は実証済みです。
玄関先やクーラーの室外機、家の外壁などへ貯めていた雨水をぶっかけましょう!
 ひまわり
ひまわり
秋の節気
【8月】に属する節気
立秋(りっしゅう)

8月8日頃
秋の始まりへの季節の変わり目。
暦の上では秋ですが、実感はまだまだかなり暑い日が続きます。
立秋以降の暑さを「残暑」と呼ぶ。
立秋後は、「暑中見舞い」ではなく、「残暑見舞い」に変わります。
【京都五山送り火】
祇園祭に並ぶ京都の夏の伝統行事。
盆の行事として、現世に迎えたお精霊を再び浄土に送る意味がある。
①『大』文字 京都市左京区浄土寺大文字山
②『妙・法』文字 京都市左京区松ヶ崎西山・東山
③『船』形 京都市北区西賀茂船山
④左『大』文字 京都市北区大北山左大文字山
⑤『鳥居』形 京都市右京区嵯峨鳥居本曼陀羅山
五文字だと思っていましたが、「妙・法」で六文字あるんですね⁉️
知りませんでした!
処暑(しょしょ)

8月23日頃
「処」という漢字は、「落ち着く・おさまる」の意味があり、暑さが収まってくるという頃です。
【二百十日(にひゃくとおか)】
台風が来る確率が高い「農家の厄日」として知られる。
立春から数えて210日目(今年は8月31日)
【防災の日】
1923年9月1日発生の関東大地震の慰霊日
死者・行方不明者は推定10万5,000人
【地蔵盆】
近畿地方を中心に行われており、「地蔵菩薩」の縁日(8月24日)を中心にした3日間。
町内の地蔵さんにお供物をしてまつる、子どもたちが主役の地域の行事です。
【9月】に属する節気
白露(はくろ)

9月8日頃
草花に朝露が付き始め秋を感じだす頃。
【二百二十日(にひゃくはつか)】
荒天が多く台風がきやすい時期。
前回の処暑で紹介した二百十日と同じく、「農家の厄日」として知られる。
立春から数えて220日目(今年は9月10日)
【中秋の名月】
今年は9月17日、旧暦8月15日の十五夜にお月見をするならわしです。
旧暦では、新月(朔月ともいう)から数えて15日目の夜をすべて十五夜と呼ぶ。
月見団子を供えるなどは、平安時代に中国から伝わった風習。
秋分(しゅうぶん)

9月23日頃
秋分と同じく、昼と夜の時間が等しくなります。
秋分の前後3日を含めた7日間を「お彼岸」と言います。
国立天文台で和歌山の日の出と日の入りを調べてみました。
日の出 05:47
日の入り 17:56
和歌山の事実 昼間が12時間9分で昼間の方がまだ長かった。
またしても、何十年と信じてきたことが覆った瞬間でした。
【お彼岸】
秋分の日を中日(ちゅうにち)として、9月19日が「彼岸入り」、9月25日が「彼岸明け」、計7日間を「彼岸」、「秋のお彼岸」ともいう。
この期間に行う仏事を「彼岸会(ひがんえ)」といいます。
【10月】に属する節気
寒露(かんろ)

10月8日頃
朝晩が冷え込む頃
食欲の秋の頃
【神嘗祭(かんなめさい)】
神嘗祭は、神宮(伊勢神宮)で10月15日~17日に行われる。
約2000年の歴史を持つ神宮でも最も古い由緒をもち、天皇陛下の大御心を体して、天照大御神に新穀を奉り収穫の感謝を捧げる最も重要なお祭り。
その年に収穫された新穀を最初に天照大御神にささげて、御恵みに感謝する。
古来、お米を主食として生きてきた日本人にとって重要な祭儀 翌11月に天皇陛下は新嘗祭を行われる。
霜降(そうこう)

10月24日頃
朝露に代わり霜が降りる頃
朝方には気温が大きく冷え込み、凍った霜が草木や霜柱として見られる。
紅葉前線が北や標高の高い山から始まり南下する.。
【銀杏】
街路樹にも多く使われるイチョウの果実。
「葉」は漢方薬として用いられ血流改善などに効果あり、「種(食用の部分)」は夜尿症対策に効果。 生のままではとても臭く、皮膚がかぶれる人もいる。
【シクラメン】
球根、多年草。 開花期は、10月~3月。
品種により、冬場に庭植えできる種類がある。
酔うと布施明の「シクラメンのかほり」を歌う人がいる。
【秋鮭】
オホーツク海などを数年回遊した後、秋に日本の川へ産卵に戻ってくる白鮭のこと。
クマの好物
冬の節気
【11月】に属する節気
立冬(りっとう)

11月7日頃
暦の上では冬が始まる頃
冬の準備に忙しくなります。
【木枯らし】
晩秋から初冬にかけて西高東低の冬型の気圧配置になり、風速8m以上の北寄りの風が吹くと「木枯らし1号」と発表される。
ちなみに、2号、3号はありません。
豆知識:東京地方と近畿地方では基準が異なり、他の地域では発表されない。
【亥の子(いのこ)】
亥の子とは、「亥の月」の最初の亥の日のこと。
亥の月とは旧暦の10月なので、現在の新暦では11月になる。
「亥の子の日」は今日11月7日。
イノシシは火を免れるとの言い伝えから「炬燵開き」をする。
小雪(しょうせつ)

11月22日頃
寒さが増してくる頃。
日中の温かい日は「小春日和」と呼ばれる。
【勤労感謝の日】
元は新嘗祭「勤労をたつとび、生産を祝い、国民がたがいに感謝し合う」が趣旨。
【新嘗祭(にいなめさい)】
新嘗祭は「しんじょうさい」ともいい、「新」は新穀を「嘗」はお召し上がりいただくことを意味し、収穫された新穀を神に奉り、その恵みに感謝し、国家安泰、国民の繁栄をお祈りします。
現在、毎年11月23日に宮中を始め、日本全国の神社で行われる。
特に宮中では、天皇陛下が自らお育てになった新穀を奉るとともに、御親らもその新穀をお召し上がりになります。
*神宮(伊勢神宮)のHP参照
【12月】に属する節気
大雪(たいせつ)

12月7日頃
たくさんの雪が振り始める頃。
「冬将軍」という言葉も聞こえだす。
【冬将軍】
「シベリア寒気団」という。
シベリアから吹き込む北西の風で、日本海側には大雪を太平洋側には乾燥した空っ風をもたらします。
冬将軍の由来は、19世紀の初めにナポレオンによるロシア侵攻の際、厳寒が原因で敗退したことによる。
【雪吊り】
豪雪地帯などの雪国では、積雪の重みで木の枝が折れないようにする。
冬至(とうじ)

12月21日頃
昼間の時間が一番短くなり、夜の時間が一番長くなる。
和歌山市の日の出と日の入りを調べてみました。
日の出 07:01
日の入り 16:53
和歌山の真実 昼間が9時間52分で昼間の方がやはり短い。
ちなみに、夏至の昼間の時間は14時間27分あります。
その差は、なんと4時間35分
年末になると、「もう一年が経つ早いな」と感じるに原因の一つかも知れませんね
【ゆず湯】
「冬至に柚子湯に入れば風邪を引かない」と言われる。
体の芯から温まることに加え、良い香りのため調子に乗って長風呂してしまう日。
【1月】に属する節気
小寒(しょうかん)

1月5日頃
寒さが厳しくなる頃。「寒の入り」とも言う。
この日以降は「寒中見舞い」となります。
【年賀状】
年賀状は松の内(1月1日~7日)に出すものなので、松の内を過ぎれば「寒中見舞い」となる。
喪中の方へのご挨拶も「寒中見舞い」が良い。
年賀状を出す人は年々減っています。
ピークは2003年の44億5,936万枚、2025年用の当初発行枚数は10億7,000万枚と大幅な減少。
さらに、2024年には郵便料金が改定されました。
63円→85円となった影響もありそうです。
私も、ラインで十分だと思っています。
大寒(だいかん)

1月20日頃
冷え込み・寒さ共に厳しい頃。
小寒から大寒を「寒の内」という。
【寒稽古】
滝に打たれながら、海に浸かりながら武道の鍛錬をします。
本当は指導者もやりたくないが、やらなしゃーない年間行事。
誰も得をしない慣習。
【大寒みそぎ】
滝の水など冷水につかり心身を清める行事です。
私はあったかい風呂が大好きです。
寒い時期なのに、寒さを存分に体験する行事が多い。
 kou
kou